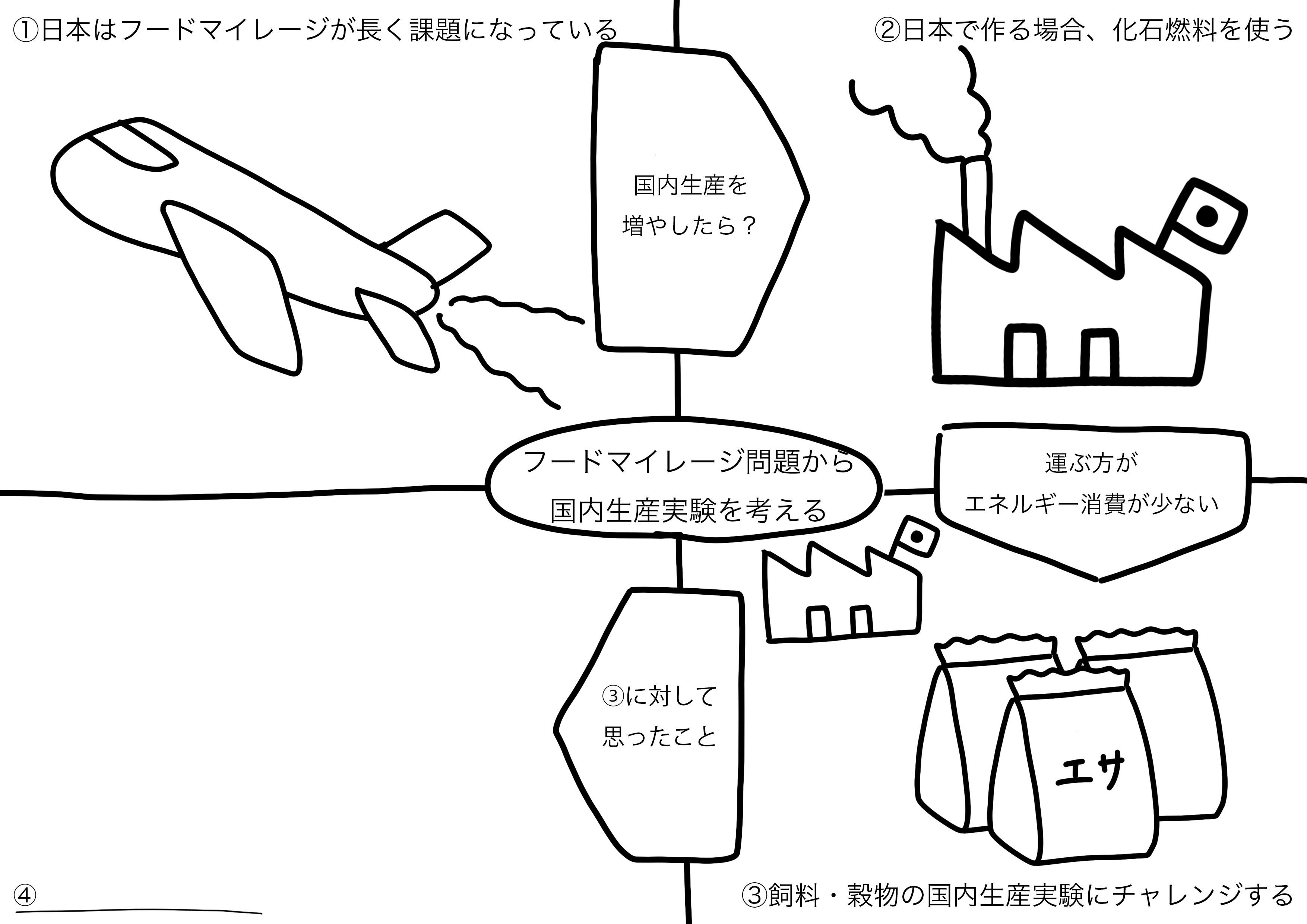社会全体でケアする。
展示全体の情報はこちらからご覧いただけます。
ーすされる手遊びで未来のケアを体感。
1つ目に紹介するのは、折り鶴、おにぎり、お手玉の3つそれぞれを”2人”でやってもらう参加型の作品「すされる手遊び」です。
みらいリビングラボは、子育てや介護などのケア研究を通じ「社会全体のケア」を目指しています。しかし、大規模な視点では具体的なアクションが見えにくいことが分かりました。そのため、まずは2人の間のケアから改めて考え直せないかと制作したのが本作品です。
ケアにはケア「する」側と「される」側がいます。これは当たり前な一方、ケアする側が負担し、される側が負担される非対称な関係に繋がります。 そこで、本作品では「二人のあいだのケア」に着目。相互にケアし合う状態を「すされる」とし、「する」側と「される」側の非対称な関係のあり方を見直す試みです。
これらから、「ケアは常にする・される側が互いに作用し合う」という認識が、「社会全体のケア」に近づくと考えました。そして出来た作品が、する・されるを一度に味わう「すされる手遊び」です。
実際に、ご来場された親子の声かけしながら一緒に作る姿は、想像よりずっとケアを考えさせられるものでした。親子でおにぎりを作るだけでも、子供の思い浮かべるおにぎりを聞き、一緒に理想に近づける親子がいれば、綺麗な三角を作る方法を子供に教える親子がいたり、出来たおにぎりや折り鶴の数だけ、親子の関係があると知りました。もし自分が子どもや親と作ったら、どんなおにぎりや折り鶴ができるでしょうか。

ー研究へのリアルな反応が見れた!

2つ目は、中谷桃子研究室所属の学生が展示した作品「VR乳児ふれあい体験」です。
現在、日本の子育て課題で「少子化対策」「子育ての社会化」があり、若者の関心を高めることが重要で、子どもふれあい体験教室もあります。しかし、機会が少なく、泣く子どもでネガティブに感じることもあります。そこで、乳児の笑顔や仕草を取り入れたVRの仮想体験で、ポジティブな効果を検証したいと考えました。
制作途中のため赤ちゃんと触れあいは叶いませんでしたが、実際にVR内の赤ちゃんと対面した人のリアルな反応が見られました。これは研究の必要性を感じられ、研究としても価値ある機会となりました。
ー展示をリアルタイムで進化
最後は、会場で唯一ワークショップが行われたブースです。こちらも中谷桃子研究室所属の学生が中心で行われた小学生向けワークショップです。未来のおもちゃを考えるワークショップは2日間計6回開催。多くの方にご参加いただき、大変活気のある場となりました。作られた未来のおもちゃは会場に設置され、リアルタイムで展示を進化させる作品にもなりました。

【未来のくらしをのぞく展】

開催日時:2024年11月3日(日)-11月4日(月) 10:00-18:30
開催場所:東京科学大学 大岡山キャンパス
イベント内容:展示、ワークショップ
主催者:みらいリビングラボ
問い合わせ先:みらいリビングラボ公式Instagram